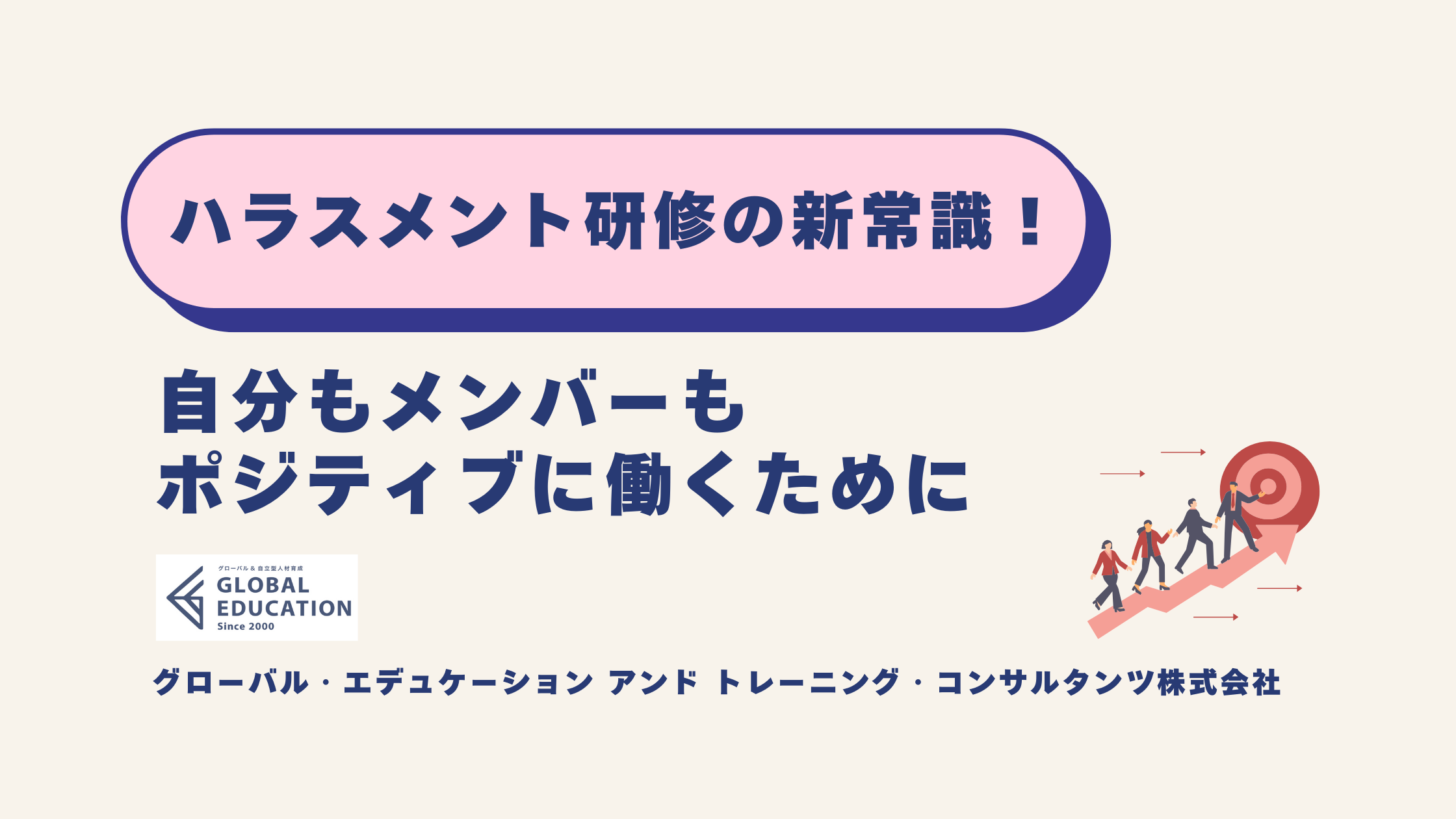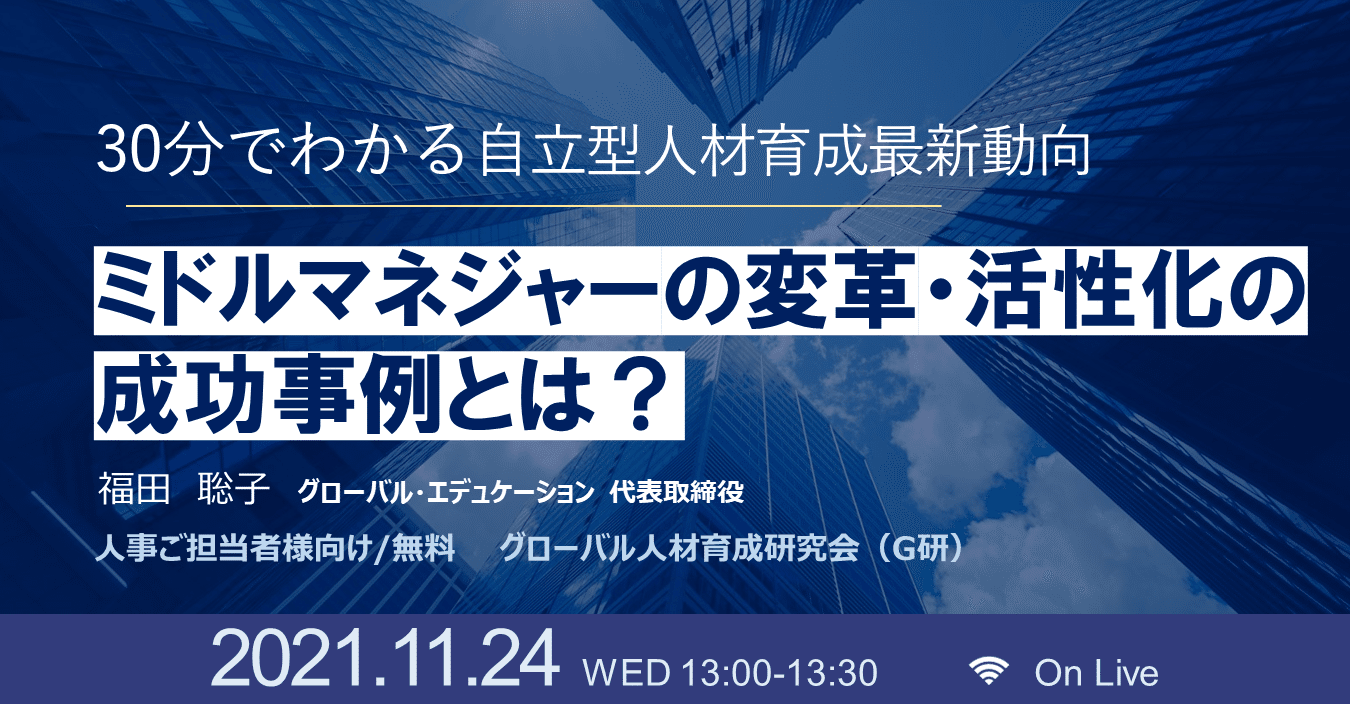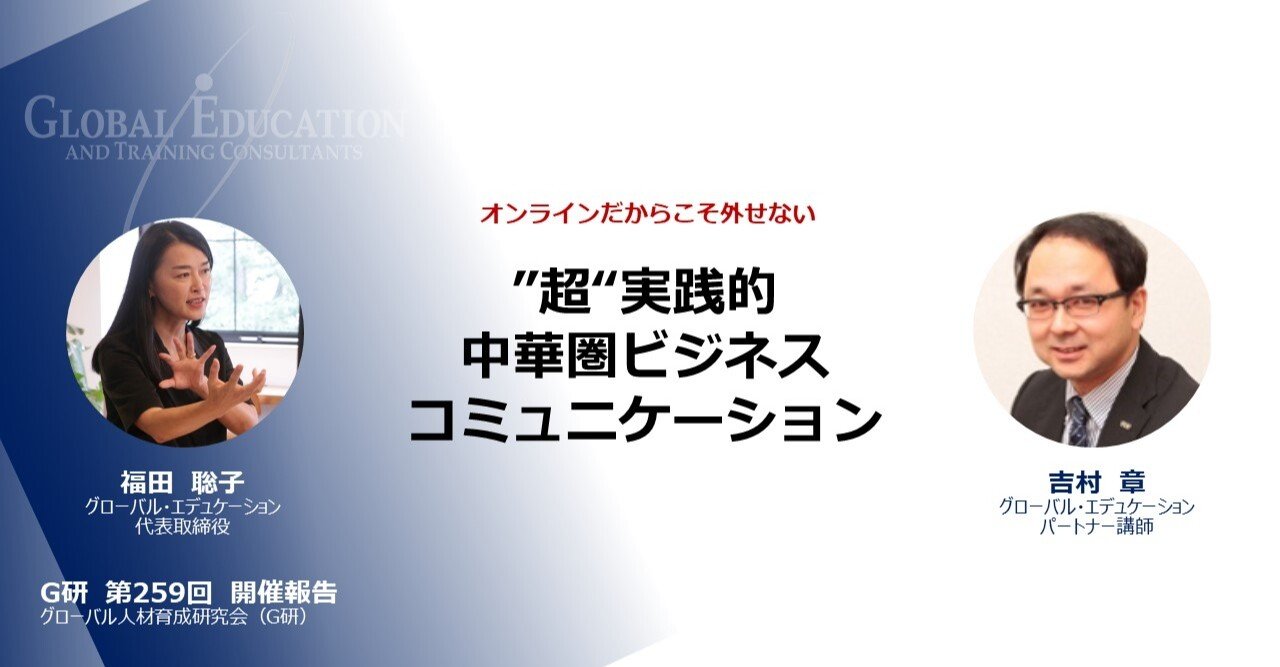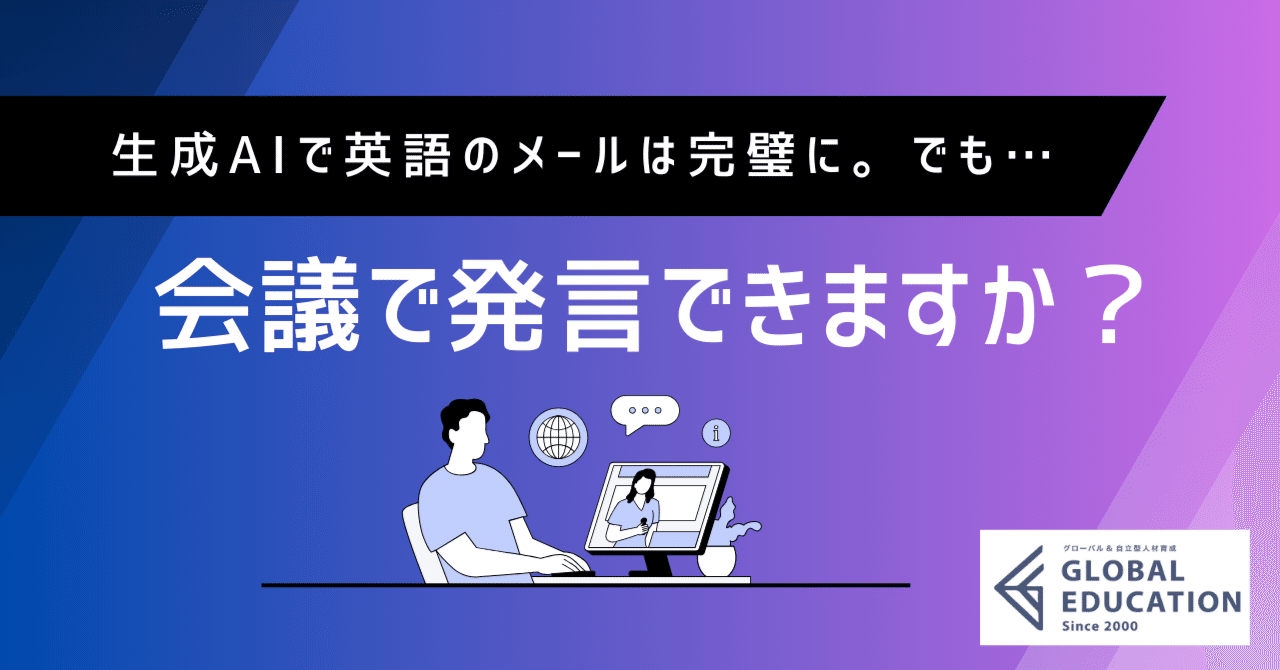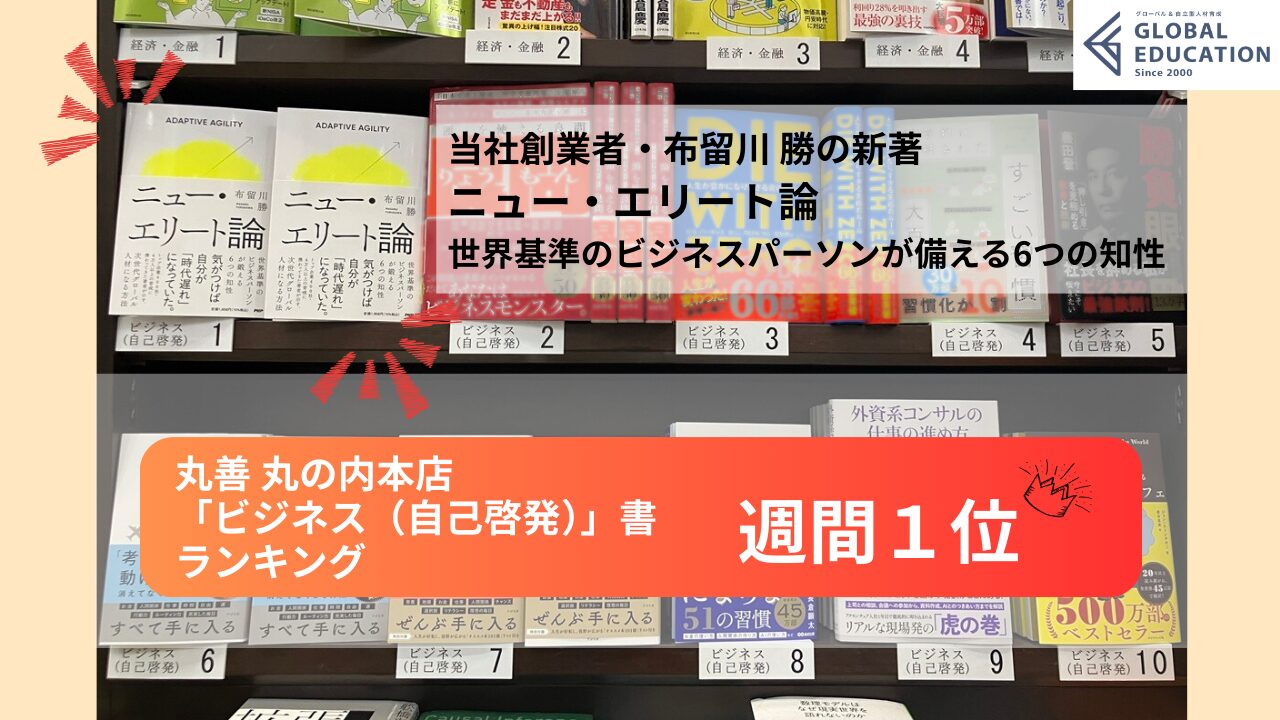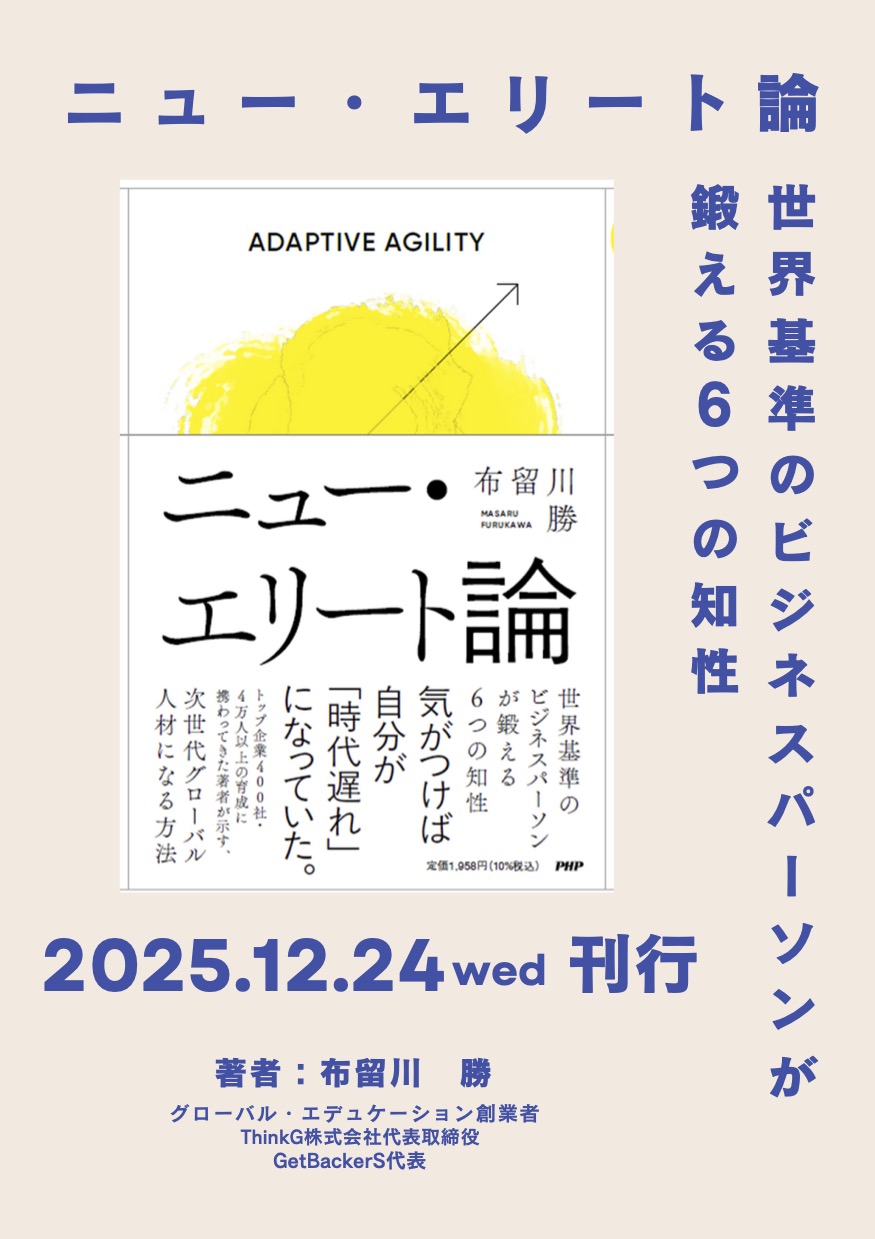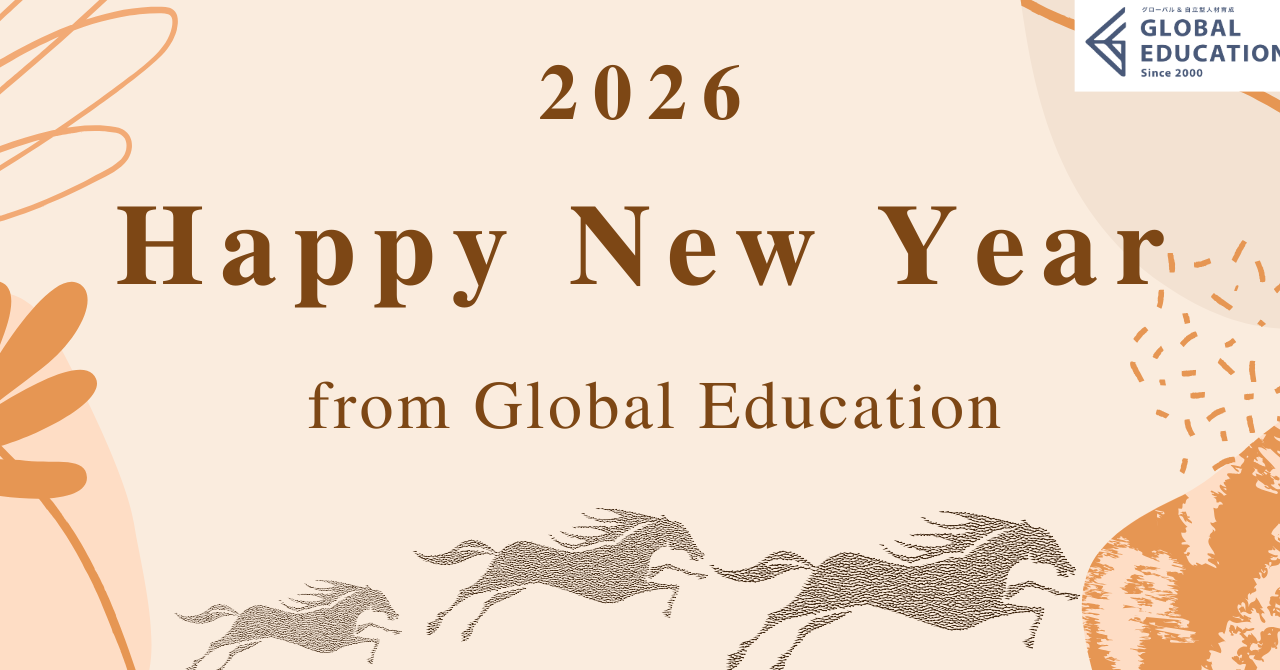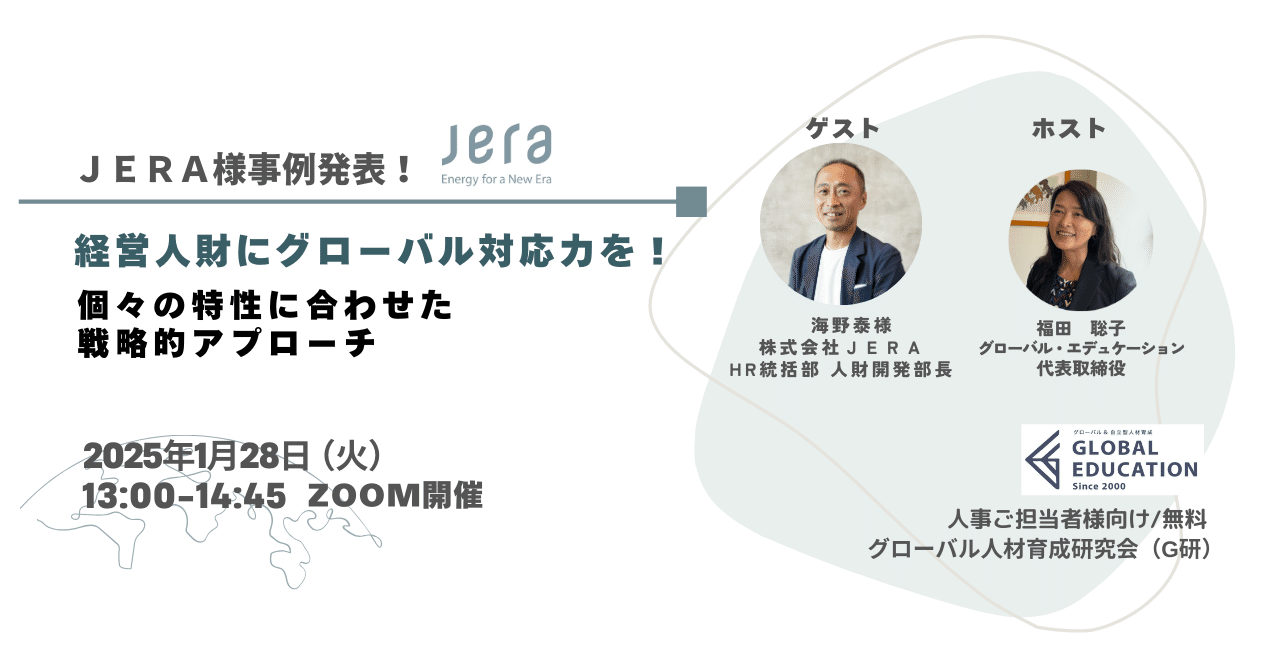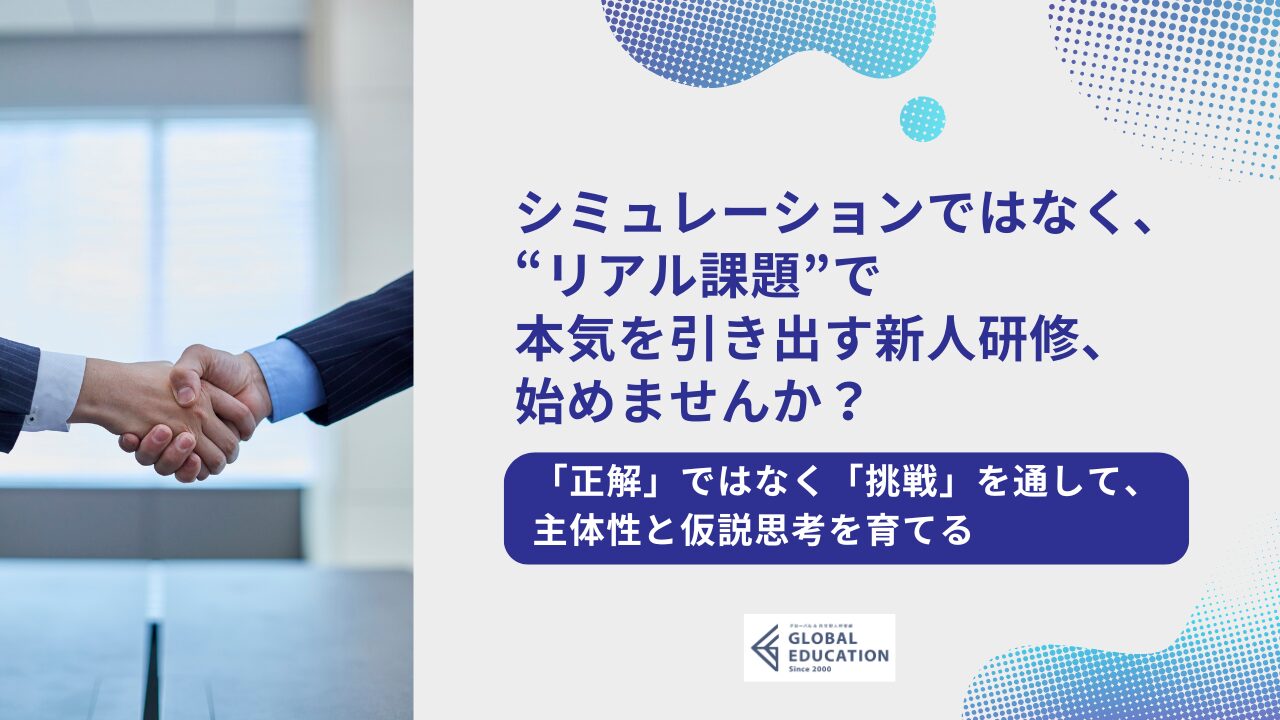こんにちは!グローバル・エデュケーションです。
最近、トップマネジメントを含む全マネジメント層へのハラスメント研修に関する
ご相談が急増しています。各社でも意識が高まっているのではないでしょうか。
実施いただいたお客様からは「ハラスメント関連のワークショップで外部のベンダーを使ったのは初めて」とお聞きしました。
これまでは内部で完結すべきものだと思われていたようですが、客観的な視点と安心できる場づくりがあってこそ、
より本質的な対話が生まれるのではないでしょうか。
みなさんは、どのような対策に取り組まれている、あるいは検討されていますか?
これまでの多くのいわゆる”ハラスメント研修”は、
緊急対応型で、弁護士や社内講師が一方的に注意喚起を行う形式が中心でした。
その結果、「これもダメ」「あれもダメ」というネガティブなメッセージが強調され、
マネジメント層は「何をしてもリスクになる・・」と感じ、
メンバーとの関係性がぎこちなくなってしまう。
そんな閉塞感を生んでいませんか?
しかし、今求められているのは、
「NG回避」から「チームの強みを引き出すリーダーシップ」への転換です。
■これまでの一般的なハラスメント研修:
目的: 法令遵守・リスク回避
形式: 弁護士や社内講師による一方向な注意喚起
内容: 「これもNG」「それも危険」といった禁止事項の列挙、注意喚起
結果:
・管理職が委縮し、部下やチームメンバーとの関係がぎこちなくなる
・「何をしてもリスク」と感じ、対話を避けるように研修が“他人事”として受け取られ、実践につながらない
■これからのハラスメント研修:
目的: チームの関係性を深め、ポジティブに働く土台をつくる
形式: 対話型・体験型ワークショップ
内容:
・自分の言動を客観視する、「俯瞰力」を育む
・善意の言動がハラスメントになるリスクへの気づき
・「レッドカード行動」など具体的で実践的な学び+アクションプランの制定
効果:
・管理職が安心して関わり、部下やチームメンバーとの関係性が好転
・チームに共感と相互理解が生まれ、生産性が向上
・「NG回避」から「関係構築」へと意識が変化
ハラスメントの多くは、「相手を傷つけよう」という悪意から生まれるものではありません。
善意や使命感からくる言動が、無意識に相手を傷つけてしまう場合もあります。
だからこそ必要なのは、自分の言動を一歩引いて客観的に見つめ直す「俯瞰力」。
とくに真面目で成果にコミットするリーダーほど、
意図せず相手にプレッシャーをかけてしまうことがあります。
研修の場においては、リスクマネジメントにとどまらず、対話を通して自分のスタイルを見直し、
チームメンバーや部下とのより良い関わり方を考えることが重要です。
■実際にセッションを受けられた方からは、こんなお声をいただいています!
”「これをやったらレッドカード」コーナーが印象的でした。
日頃何気なく使っていた言葉が実はハラスメントになり得る言葉であったこと、
相手を思いやって発した言葉も実は問題になりうると気付かされたこと。
日々のコミュニケーションの大事さ、客観的にみる力をつけていくことが
重要であることを体感しました。”
”最初は暗い気持ちで参加していたのですが、
ディスカッションで気づいたら白熱、 非常に”楽しかった”です。
センシティブなテーマだからこそ、普段そこまで踏み込んだ会話をしない為、
より深くチーム同士の共感や学びを知ることができた。
チームメンバーがどうしたらポジティブに働けるか?という発想の転換をすることができる
セッションでした。”
■担当コーディネーターのコメント:
特に好評だったのは、「もめている相手との向き合い方」や
「はっきり言わなければいけない時の効果的な伝え方」など、
管理職に不可欠な現場での実践的な対話スキルを体験いただいた点でした。
センシティブなテーマだからこそ、未来に向けたオープンな対話が鍵になると考えています。
研修では「この場合って、皆さんどうしてますか?」とそれぞれが自由闊達に問いかけ、
管理職の方々が安心して、(時に笑いも起こりながら!)意見交換していたのがとても印象的でした!
「ハラスメント研修をやったはいいものの、カルチャーが変わらない…」
「管理職が前向きに参加し、一体感を感じられるような内容にしたい」
こうしたお悩みをお持ちの方、ぜひお気軽にご相談ください!